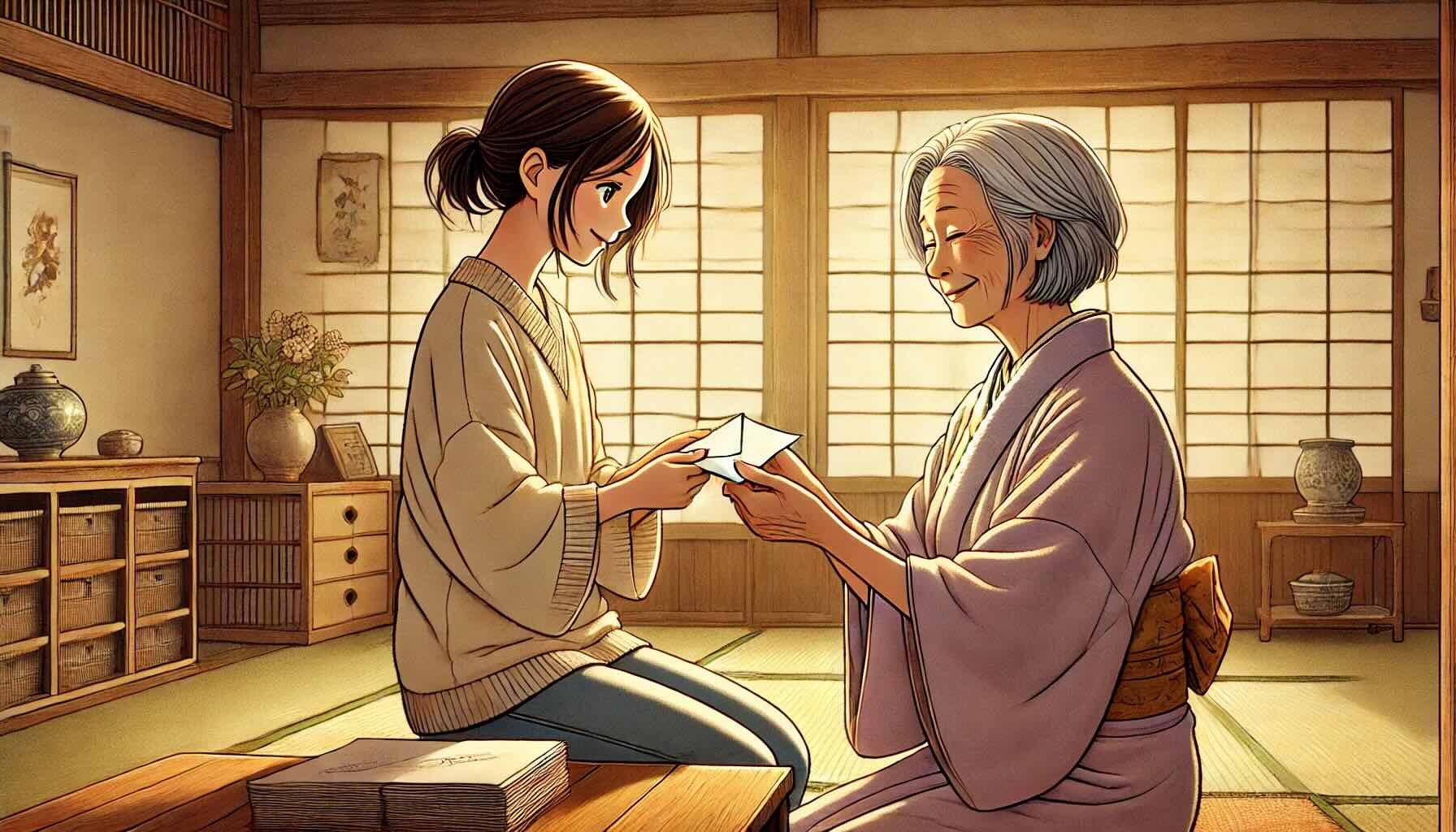「母の日って、いつまでプレゼントをあげればいいんだろう?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
年齢や親との距離感、生活スタイルの変化によって、毎年のようにやってくる母の日がふと“迷いのイベント”になることもありますよね。
この記事では、「母の日 いつまであげる?」という疑問に対して、やめどきの見極め方や新しい感謝の伝え方を、やさしく丁寧に解説しています。
形式にとらわれない、でもちゃんと心が伝わる方法を見つけたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
母の日のプレゼントはいつまであげるべき?
母の日のプレゼントはいつまであげるべき?という疑問についてお答えします。
それでは、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
①年齢や家庭環境によって異なる
「母の日のプレゼントって、何歳まであげたらいいんだろう?」って、意外とみんな一度は悩んだことがあると思います。
結論からいうと、「絶対に○歳まで」というルールはありません。
それぞれの家庭環境や親子関係によって、本当にバラバラなんです。
例えば、20代や30代の人だとまだまだ現役で「母に感謝を伝えたい!」という気持ちが強くて、毎年欠かさずプレゼントを用意する人も多いです。
一方で、40代や50代になると、自分の家庭を持って忙しくなり、母の日を簡略化したり、やめようかと考える人も増えてきます。
また、母親が高齢になってくると、「もう何もいらないよ」と言われるケースもあります。
このタイミングで「もうやめてもいいかな?」と考える方も多いんですよね。
だからこそ、「他の人がどうしているか」よりも、「自分と母の関係性にとって自然な形って何か?」を考えるのが一番大事です。
筆者も40代で、母は70代後半。最近はカーネーションではなく、毎年お手紙と好物の甘酒を届けています。こんな形でも十分喜ばれますよ。
②「もういらない」と言われた時の対応
「母の日のプレゼント、もういらないって言われちゃった……」なんて経験ありませんか?
これ、結構ショックですよね。
でも、これって「プレゼントが嬉しくない」わけじゃなくて、「気を遣わせたくない」とか「子どもに負担をかけたくない」っていう、親心からの言葉であることが多いんです。
だから、「わかった、じゃあやめるね」ってあっさり終わりにするのはちょっと早いかも。
そんな時は、「じゃあ、今年は手紙だけにするね」とか、「一緒にごはん食べに行こうか」みたいに、負担にならない方法で気持ちを伝えてみてください。
特に高齢のお母さんほど、プレゼントより“気遣い”の方が心に響くこともあります。
実際、「何もいらないって言ったのに、あなたが来てくれただけで嬉しかったわ」と言われた人も多いんですよ。
要は「モノ」じゃなくて「気持ち」。
感謝の伝え方をちょっと工夫するだけで、関係性もずっと温かく保てますよ。
筆者もある年、母に手作りの写真カードを送ったら泣いて喜ばれました。「いらない」って言葉は、むしろ「もう形式的なのはいいから、本音の気持ちをくれ」というサインなのかもしれませんね。
③義母への母の日ギフトはどうする?
「実母にはあげるけど、義母にはどうしよう?」って悩む方もすごく多いです。
義母との関係って、距離感が難しいんですよね。
あげないと角が立ちそうだし、あげすぎても気を遣わせてしまう。
この微妙なバランスが本当に悩ましいポイント。
基本的には、「最初にやったら続ける」のが礼儀として自然です。
だからこそ、義母へのプレゼントを始める時は「どこまで続けられるか」を想定しておくのが大事。
また、夫婦で話し合って方針を合わせるのもすごく重要です。
たとえば、「毎年お花とメッセージカードだけにする」と決めておくと、お互いストレスが少ないです。
義母へのプレゼントをやめたい時は、誕生日や敬老の日など他の行事と統一したり、気持ちをカードや電話で伝えるのもひとつの方法ですよ。
私も最初は悩みましたが、今は義母には夫から簡単なプレゼントを渡してもらってます。「嫁から」は重く感じる方もいるので、夫に任せるスタイル、おすすめですよ〜!
④やめどきのサインを見極める
母の日をやめたいと感じる理由って、人それぞれあると思います。
たとえば「感謝の気持ちはあるけど、経済的にきつい」「親が高齢であまり物を喜ばなくなった」「距離的に会えない」などなど。
そんな時、「プレゼントをやめてもいいかな?」と考えるのは全然アリです。
ただ、その判断をする時は、お母さんの反応や普段の会話をちょっとだけ観察してみてください。
たとえば、「今年は何もしなくていいからね」とか、「毎年気を遣わせてごめんね」みたいな言葉が出てきたら、それは“やめどき”のサインかもしれません。
でも、やめる=何もしない、ということではありません。
やめる場合でも、「代わりに毎年電話をする」とか、「季節の便りを送る」など、気持ちの伝え方はちゃんと持っておくと、関係がより良好に保てますよ。
大事なのは、形式じゃなくて「心」。やめるかどうか悩んでるあなたの優しさこそが、すでにプレゼントになってると思いますよ!
母の日をやめるタイミングと注意点
母の日をやめるタイミングと注意点について詳しく解説していきます。
それでは、それぞれのポイントを掘り下げていきましょう!
①やめる前に一度話し合う
母の日をやめようかな…って思ったとき、まず大事なのは「話すこと」なんですよね。
いきなりスパッとやめちゃうと、相手によっては「急に冷たくなった…?」なんて思わせてしまうこともあります。
それが原因でモヤっとした空気になるのは、やっぱり避けたいところ。
「最近、母の日も年々大変になってきちゃってね…」とか、「これからは違う形で感謝を伝えたいなと思ってて」みたいに、やんわり伝えると相手も構えずに受け取ってくれやすいです。
ポイントは、いきなり「やめたい」ではなく、「もっといい形にしたい」と伝えること。
そうすると、お母さん側も「それなら全然いいよ〜」って快く納得してくれることが多いんですよ。
大切なことだからこそ、ちゃんと話して、お互いの気持ちを確認してからの判断がベストですね。
私の友人は、お母さんに「これからは一緒にご飯行くことにしようか」と提案したそうです。結果、母の日をやめたのに、今まで以上に良い関係になったって言ってましたよ!
②感謝の気持ちだけ伝えるのもアリ
プレゼントはやめたいけど、何もしないのも気まずい…って思ったことありませんか?
そんなときは、「ありがとう」の一言だけでも十分です。
本当に。
たとえば、LINEで一言「いつもありがとう」と送るだけでも、お母さんはちゃんと受け取ってくれます。
むしろ、「物より気持ちが嬉しい」っていう人も多いんですよね。
お金や時間をかけることよりも、「自分のことを思い出してくれた」っていう事実が、母親にとっては一番嬉しいことなんです。
だからこそ、無理してプレゼントを続けるよりも、無理のない範囲で「感謝だけ伝える」という選択肢、すごくおすすめです。
筆者の母も、「プレゼントはいらないけど、あなたの気持ちだけで十分」って何度も言ってくれました。素直な言葉って、それだけでじゅうぶん力がありますよね。
③兄弟姉妹と相談して足並みを揃える
これ、意外と見落としがちなんですけど、母の日をやめるときは「兄弟姉妹と歩調を合わせる」のがすっごく大事なんです。
というのも、自分だけやめて、他の兄弟がプレゼントを渡してたら…
「え?○○はくれたのに、あなたは何もないの?」なんて、ちょっとした誤解が生まれかねないんですよね。
だから、やめたいと思ったら、まずは兄弟や姉妹に一言相談しておくとスムーズ。
「今年から母の日どうしてる?やめようか迷ってて」みたいに軽く聞いてみてください。
話が合えば一緒にやめる流れも作れるし、逆に「まだ続けたい」という意見があれば、プレゼントの内容を相談して合わせることもできます。
兄弟間のバランスって、意外と親の印象に大きく影響するからこそ、ちょっとした配慮が後々大きな差になりますよ。
私の家では、姉と「もう母の日はカードと電話にしようか」って相談しました。母も「みんなの気持ちがそろってるのが一番嬉しい」って笑顔でしたよ〜!
④フェードアウトするなら時期と方法に配慮を
プレゼントをやめるにも、「スパッとやめる」より、「徐々にやめていく」=フェードアウトって方法もあります。
たとえば、
– 高価なギフト → お花だけ
– お花 → メッセージカード
– カード → 電話やLINEで一言
というように、段階的に簡素化していくんです。
そうすれば、お母さん側も「今年はこれだけなんだ…」って違和感なく受け入れやすいんですよね。
この方法なら、「やめた」っていう強い印象を与えずに、自然に感謝のスタイルを変えていけます。
しかも、ちゃんと感謝の気持ちは残せる。
やめるときは、“自分の気持ち”だけでなく、“相手がどう受け取るか”も想像してあげられると、よりスマートな対応になります。
筆者も、最初はプレゼント→お花→カード→電話って流れでやめました。「あれ?今年は花ないのね」って母に言われたけど、「気持ちは変わらずあるよ」って言ったら嬉しそうに笑ってました。ゆるやかに変えていくの、ほんとにおすすめです。
母の日に代わる新しいカタチの感謝の伝え方
母の日に代わる新しいカタチの感謝の伝え方についてご紹介します。
「モノ」じゃなく「心」を大切にした、新しい母の日の形を見ていきましょう。
①メッセージや手紙に切り替える
「もう母の日のギフトはやめようかな…」と思っても、やっぱり感謝の気持ちは伝えたい。
そんな時にピッタリなのが、“メッセージ”や“手紙”という形です。
実はこれ、プレゼントよりも何倍も心に響くことがあるんですよね。
普段は言えないような、「ありがとう」「元気でいてね」「感謝してるよ」という言葉を、あえて紙に書いて伝える。
このひと手間が、本当に大きな意味を持つんです。
たとえば、便せん一枚でもいいんです。
ちょっとした近況報告や、母との思い出を一言添えるだけで、受け取った側は「読んで涙が出た…」なんてことも珍しくありません。
さらに、LINEやメールでも大丈夫。
大切なのは「言葉にすること」なので、形式にはこだわらなくてOK。
母の日だからこそ、「ありがとう」の気持ちを、あらためて文章で届けてみてください。
私も最近は、毎年手紙を送っています。「毎年もらう花も嬉しかったけど、手紙は何度も読み返せるから宝物だよ」と母に言われて、涙腺崩壊でした…!
②誕生日や父の日とまとめて渡す
「イベントが多すぎて大変…」という方におすすめなのが、母の日を“ほかの行事とまとめる”スタイル。
例えば、
– 母の日+父の日
– 母の日+誕生日
– 敬老の日と一緒に
というふうに、イベントを一本化するんです。
この方法、実は親世代にも好評なんです。
理由は、「気を遣わずに済む」「まとめてもらえる方がラク」だから。
特に年配のご両親は、「そんなにしなくていいよ〜」というタイプが多いので、感謝の気持ちを“イベント単位”で届けるのがちょうど良かったりします。
一度にしっかり気持ちを伝えることで、無理なく続けられるし、お互いにとって負担も減りますよ。
筆者は毎年、6月の父の日の時期に「母の日&父の日合同ランチ会」を開催してます!まとめることで負担がグッと減るし、両親も喜んでくれるので一石二鳥です♪
③旅行や食事など体験型のギフトにする
「モノをあげるより、一緒に過ごす時間を贈りたい」って人にぴったりなのが、“体験型のプレゼント”です。
たとえば、こんなギフトがあります。
| 体験型ギフト | ポイント |
|---|---|
| ランチやディナーに招待 | 気軽にできて会話も弾む |
| 一緒に温泉旅行 | 非日常の思い出が作れる |
| コンサートや舞台観劇 | 共通の趣味がある人に最適 |
| 料理教室やワークショップ | 一緒に学ぶ体験が心を近づける |
一緒に過ごすことで「ありがとう」がもっと深く伝わるし、何より母親の記憶に残るんですよね。
最近は、ギフトカタログや体験ギフトチケットも充実してるので、「どれにするか悩む〜!」って人も選びやすくなっています。
私の母は旅行が好きなので、数年に一度、母娘で1泊旅行に行ってます。「これが一番のプレゼント」と毎回言ってくれて、こちらも心が満たされますよ〜!
④無理せずできる範囲で継続する
最後に大事なのは、「頑張りすぎない」ってこと。
母の日って、感謝を伝える大切な日ではあるけれど、それが「苦痛」になったら意味がないですよね。
だからこそ、自分の生活や気持ちに合わせて、“できる範囲”で続けていくことが一番のポイント。
年によっては忙しかったり、体調がすぐれなかったりして、準備ができないときもあると思います。
そういうときは、無理にしなくてもいいんです。
「今年は遅れちゃってごめんね」って一言添えるだけで、ちゃんと気持ちは伝わります。
完璧を目指さず、肩の力を抜いて「続けられるスタイル」を作っていく。
それが、母の日と上手に付き合うコツですよ。
私も一時期、忙しくてなにもできなかった年がありました。でも母から「気持ちだけで十分」と言ってもらえて、すごく救われました。「無理なく続ける」って、本当に大事な視点です!
まとめ|母の日 いつまであげるのが正解?
母の日のプレゼントを「いつまであげるべきか?」という疑問には、明確な正解はありません。
大切なのは、相手との関係性やライフスタイルの変化に合わせて、“心地よいかたち”で感謝を伝え続けること。
プレゼントをやめるタイミングに悩んだら、一度気持ちを伝えてから徐々にフェードアウトしたり、無理のない範囲でメッセージや体験を贈るのも素敵な選択肢です。
「ありがとう」の気持ちがあれば、どんな形でもきっと伝わりますよ。